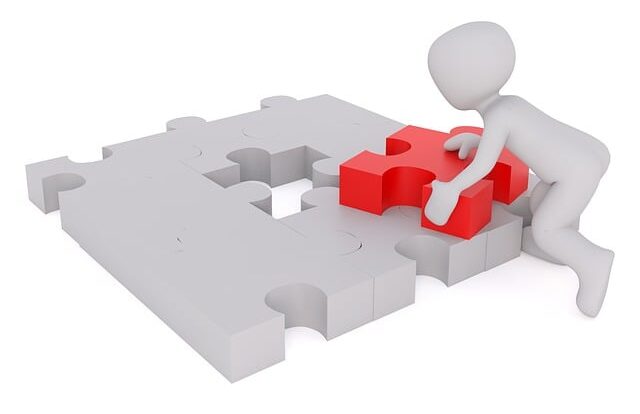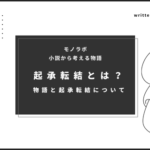本ブログでは「物語」に関わるコンテンツをメインに取り扱っていますが、そもそも、「物語」というものについて正確に説明できる人はどれくらいいるのでしょうか。
当然ですが、本職の作家などの、仕事として「物語」を扱う人たちは、それぞれ自身の中にある物語の定義があるかもしれません。
これはおよそ、アマチュアとして作品を世に出し続ける人たちも同じでしょう。
今回は、このブログで取り扱っている「物語」について、筆者の個人的な考え方についてご紹介させていただきます。
もちろん、個々にある「物語」の捉え方というものはあくまでも一例ですので、同じく創作に携わる方の中で、自身の中の物語を考える一助となれば幸いです。
そもそも物語とは?
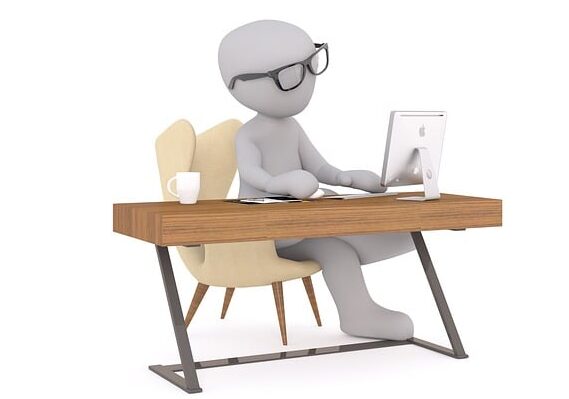
それでは早速物語というものについて考えていきましょう。
まず最初に、「物語」の言葉自体について、辞書から引用させていただきます。
物語の解説
goo辞書-物語(ものがたり) とは? 意味・読み方・使い方より
1.様々な事柄について話すこと
3.文学形態の一つ。作者の見聞や想像をもとに、人物・事件について語る形式で叙述した散文の文学作品。
こちらの辞書ではいくつか「物語」の言葉の意味を解説していますが、この記事で取り扱う意味としては、「3」の意味になります。
これを簡単に要約すると、「物語とは、作り手が経験や知識を元に、特定の出来事の顛末を語ること」であるとされています。
これは、恐らく多くの人が無意識に持っているであろう物語の意味となります。
言葉として説明できずとも、これは多くの人が納得できる物語における解説であると思います。
筆者自身、この解説に対してはその通りであると感じていますし、他の人に解説をするのであればそのような内容になると思います。
いわば物語とは「特定の出来事」を、それを知らない読者へ伝えていくためのものであると考えることが出来ます。
しかしながら、その「特定の出来事」を相手に伝えていくため、どのようなやり方があるのでしょうか?
これからは物語を構成している要素をいくつか考えていきましょう。
物語の構成要素

一口に「物語」と言っても、そこには実に多くの種類があります。
簡単に考えても、下記のような物語の種類があると言えるでしょう。
フィクション:現実にはない、書き手の作り出した物語
ノンフィクション:現実におきた出来事を、事実のままに書き出す物語
ファクション:現実に起きたことを基盤にして、書き手の想像を交えた物語
この世の殆どの物語と呼ばれるものが、上記のいずれかに属しています。
これらは具体的な線引については、実際に文学を研究されている方々の中でも多くの意見があるかと思います。
このブログでは「現実に起きたことをありのまま伝えるものをノンフィクション」として、それ以外は「フィクション」として捉えるざっくりとした解釈で話を進めていきます。
また、ファクションは「現実に起きた出来事からインスピレーションを得た物語」として捉えます。
このように、物語は「現実に起きたこと」と「想像で作られたもの」という大きな種類があるわけです。
しかしながら、これらの「現実かどうか」ということも大切なのですが、物語は本当か作り物かに限らず、下のような構成要素を持っていると筆者は考えています。
物語は上の3つの要素があり、それぞれがとても大切なものになります。
これらはそれぞれの要素にはなるのですが、明確に主従関係にあると筆者は考えています。
簡単に表現すると、これらの要素には順番があります。
- 舞台(キャラクターのもととなる世界)
- キャラクター(舞台にキャラクターが乗っている)
- 物語の流れ(舞台のキャラクターが物語を作る)
これらについては各部分で細かく説明しますが、基本的に世界観というものはこのような流れを持っていると、
もちろん、どこから物語を着手するかは人によってそれぞれですが、まずは舞台の意識を漠然と持っておくと、その後訂正することも少ないかもしれません。
舞台(世界観)

物語を形作るうえで、その原型となるものが「舞台(世界観)」です。
物語として何かを語るときには、まず最初に「その世界そのもの」が必要になってきます。
どんな物語にも舞台というものが必要であり、それがどのような舞台なのかというものは、その物語事に異なっているはずです。
一般的によく用いられる舞台や物語の傾向としては、下のようなものがあるでしょう。
現代ドラマ:現代社会(現実の人間社会を元にした部分的に架空の世界)
ファンタジー作品:幻想社会(魔法の概念や他種族が共存しているという架空の世界)
これは舞台として大別して考えていますが、基本的にはこれらの考え方を軸に、その舞台がどのような場所であるかが、物語において大切な意味を持ってきます。
例として、魔法のある世界の物語では、そこで使用されている「魔法」というテクノロジーを使った物語を作ることが出来ます。
これはあくまでも、「魔法がある」という共通認識が書き手と読者の間にあるからこそ成立しています。
これが現代社会をベースにした世界観であれば、「どうして魔法なんてものがあるのか?」や、「どのような原理なのか?」などという見当外れな考えのズレが生じてしまいます。
このように、物語における「その世界がどのような場所なのか?」ということは、実を言うととても大切です。
この舞台を読み手にスムーズに伝えることこそが、物語の大切な一歩であると言えるでしょう。
物語における舞台(世界観)というものは、いわば書き手と読者の「共通認識を一致させる」ということでもあります。
キャラクター
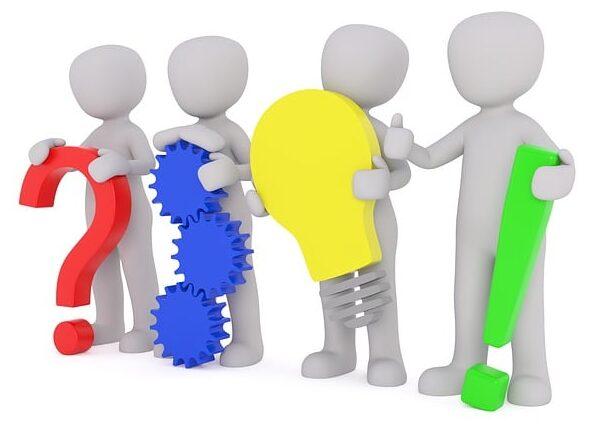
次に大切な要素としては、キャラクターが挙げられます。
物語を作っていく代表的な面々であるキャラクターですが、これは舞台があってこそ出来上がるものです。
ここで一つ、具体的な例を考えてみましょう。
(とある恋愛小説の導入として)
私、都内の高校に通う高校二年生の若松響子。クラスの中での成績は中の上くらい。顔は、自分じゃわからないけれど、周りからはよく「キレイ」って言われる。でも、クラスで一緒の幼馴染、涼宮東吾からはよく、「ブス」ってからかわれるの。それが嫌じゃないのが、なんか嫌なんだけれど。
上記の例を見れば、「日本の高校を舞台」であることがすぐに分かると思います。
ここまでベタなものは恐らくないでしょうが、この文章から読み取れるキャラクターの情報は、下のようなものが挙げられます。
- 若松というキャラクターは日本の東京に在住の高校二年生
- 学校に通っている
- クラスの中では容姿端麗とされている
- 幼馴染に涼宮東吾という男の子がいる
- 幼馴染の男の子に他の人とは違う気持ちを向けている。
このように、キャラクターだけを切り取ったとしても、そこから読み取れる情報は実はかなりのものです。
しかしながら、このキャラクターが存在できるのは「現代社会をベースにしている場所」だからこそです。
例えばこれが、魔法や他種族が存在する魔法の国で登場したら違和感の塊でしょう。
読者もこれを見て、その世界観が簡単に理解できます。世界観が存在するからこそ、これらのキャラクターも違和感なく存在できるわけです。
キャラクターは基本的に、舞台(世界観)があるからこそ存在出来ます。
幻想社会であれば、人間以外の種類の生物が存在している、ということに納得する事ができるでしょう。
逆を言えば、舞台(世界観)でのキャラクターは、しっかりと舞台に沿ったキャラクターでなければなりません。
現代的な世界観の中で、エルフのようなファンタジックなキャラクターが登場すると、違和感がノイズになってしまいます。
もちろん、どのようなキャラクターが登場するかというものは最終的にその人がどのように物語を作るかで変わります。
作品としてのノイズにならないように、しっかりとしたキャラクターと世界観は、固めておくほうが良いでしょう。
物語としての展開
ここまでの要素の中で、舞台(世界観)とキャラクターについてお話していましたが、そこからどのようにして物語が動くかということが、いわば本題になります。
舞台とキャラクターというものは、いわば物語においての大前提であり、魅力の一つです。
舞台とキャラクターが織りなす物語において、それらがどのように展開され、読み手の「面白い」に繋がっていくかということは難しい問題です。
物語としての進みは「起承転結」が非常に分かりやすい物となっています。
以前にて「起承転結」を解説した頁があるので、気になる方はそちらを御覧ください。
物語の流れや展開は上のページに譲るとして、物語は具体的にどのようなものを指しているのでしょうか。
筆者はいくつかパターンがあると思っており、下のようなものを挙げています。
- 変化 特定の出来事を通して、世界やキャラクターの変化を描く物語
- 達成 世界やキャラクターが何かしらの目的を持っており、それを達成するまでのプロセスを描く物語
- 結果 特定の出来事のなかで、世界やキャラクターが選んだものの結果を描く作品
物語にはいわゆる、「ハッピーエンド」や「バッドエンド」など、複数の種類があると思います。
しかしながら、それはあくまでも主観的なもので、作品として「何を重点的に見せるのか?」という問い掛けには答えていません。
あくまでも、物語とは「舞台の上でキャラクターたちが何を読者へ魅せるのか」ということでもあると思います。
そこが丁寧に描かれ、かつ読者が見たいと感じるカタルシスを垣間見るもの、それこそが物語の本質であると筆者は考えています。
それらを違和感なく見せる手法として、先述の「起承転結」などが用いられる場合があります。
作品として素晴らしいものを作る時、このように骨組みから考えていくということは、意外にも物語の軸を考えるうえで大切な要素になるかもしれません。
まとめ
それでは本日のまとめです。
今回の記事では、「物語」について考えていきました。
物語という言葉は非常に多く使われる言葉ですが、物語を実際に作る側に回ると、その奥深さが見えてくるものです。
特に創作物となると、そのほとんどに何かしらの物語が存在します。このような要素に分解してみると、作品の考え方も変わってくるでしょう。
このブログでは、物語や小説を軸にした記事を取り扱っています。今後共にご覧いただければ幸いです。